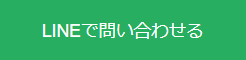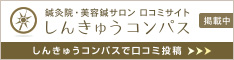更年期障害
50代女性・介護士
主訴
情緒不安定(悲嘆・焦燥感)と喉の異物感。
現病歴
職場の人間関係の変化を機に、急に悲しくなって涙が出たり、逆に激しい怒りを感じたりと情緒が安定しなくなった。喉に何かが詰まっているような不快感があり、飲み込もうとしても消えない。
既往歴
30代の頃に自律神経失調症の既往。
生活習慣
責任感の強い性格。ストレスが多く、夜は考え事をして寝付けない。
東洋医学的分析と治療経過
腎虚肝鬱証と判断し、体力を補いつつ、気の滞りを解く方針で治療を開始。
経過
- 1週: 喉のつかえ感(梅核気)が軽くなり、食事が美味しく感じられるようになった。
- 3週: 感情の起伏が穏やかになり、ため息が減った。
- 5週: 前向きな気持ちで仕事に取り組めるようになり、睡眠も深くなった。
続きはnoteで
本編では、「更年期障害」のタイプ別の詳しい原因と養生法、複数の症例の経過を解説しています。
体質からの整え方を見つけるヒントになるはずです。
排卵期出血
20代女性・会社員
主訴
排卵期の出血と、黄色の粘り気があるおりもの 。
現病歴
1年前から排卵期に5日間ほど出血し、下腹部に重だるい痛みがある 。
既往歴
過去に細菌性腟炎を繰り返した経験あり 。
生活習慣
外食が多く、お酒と辛いものを好む 。
東洋医学的分析と治療経過
湿熱証と判断し、「熱と湿気を取り除き、血を落ち着かせる」方針で治療 。
食事指導を並行し、2周期目から出血量が減少。
続きはnoteで
本編では、「排卵期出血」のタイプ別の詳しい原因と養生法、複数の症例の経過を解説しています。
排卵期出血で悩まれる方にとって、体質からの整え方を見つけるヒントになるはずです。
夢が多くて眠りが浅い
20代女性・大学院生
主訴
眠っても夢が多く、朝の疲れが抜けない。レポートや研究発表の準備で緊張し、試験前は特に夢が増える。
生活背景
-
睡眠は6時間前後だが、夢をよく見て熟睡感がない
-
昼はパンや甘い菓子で済ませることが多い
-
長時間のデスクワークで運動不足
-
生理前に疲労感と集中力低下が目立つ
東洋医学的分析
-
勉強による思考の使いすぎと、食生活の乱れで「脾(消化の力)」が弱り、気血が不足
-
気血が足りないため「心(精神を落ち着ける働き)」を支えきれず、夢が多く眠りが浅くなる
→ 「心脾両虚型」の多夢と判断
行ったこと
-
鍼灸:脾を補って気血を養い、心を落ち着ける施術を週1回
-
生活改善:
-
夜は就寝前のスマホを控え、軽い散歩を習慣化
-
甘い菓子やカフェインを減らし、消化にやさしい食事を意識
-
経過
-
2週間で夢の回数が減り、朝の倦怠感がやや改善
-
1か月で試験期でも睡眠の質が保たれるようになり、集中力が向上
-
2か月後には熟睡できる日が増え、夢を覚えていないことも多くなった
続きはnoteで
本編では、「多夢」のタイプ別の詳しい原因と養生法、複数の症例の経過を解説しています。
「寝ても寝ても休まらない」方にとって、体質からの整え方を見つけるヒントになるはずです。
寒暖差アレルギー
40代女性・事務職
主訴
季節の変わり目に、朝起きると鼻水が止まらずくしゃみが連続。検査ではアレルギー反応なし。日中も疲れやすく、午後には強い眠気が出る。
生活背景
-
朝食は菓子パンやコーヒーで済ませることが多い
-
昼食後にお腹が張りやすく、軟便ぎみ
-
デスクワーク中心で運動不足
-
睡眠は6時間前後だが、朝起きても疲れが残る
東洋医学的分析
-
不規則な食事と消化不良で「脾(消化の力)」が弱まり、体のエネルギー=気が不足
-
抵抗力が落ちたため、気温差という小さな刺激で鼻症状が出てしまう
→ 「脾気虚型」の寒暖差アレルギーと考えられる
行ったこと
-
鍼灸:脾胃を整えて気を補い、鼻の通りを改善する施術を週1回
-
生活改善:
-
朝食を温かいお粥や味噌汁に変更
-
冷たい飲み物を控え、常温や温かいお茶を摂る
-
昼休みに10分の散歩を取り入れて代謝を促す
-
経過
-
2週間で朝の連続くしゃみが減り、鼻水も軽くなる
-
1か月で午後の眠気が改善し、仕事がはかどるように
-
2か月後には季節の寒暖差があっても大きく悪化せず、安定して過ごせるようになった
続きはnoteで
本編では、寒暖差アレルギーのタイプ別の詳しい特徴と鍼灸での整え方、複数の実際の症例を解説しています。
「花粉症ではないのに鼻がつらい」という方に、体質から見直すヒントになれば幸いです。
ドライアイ
50代男性・会社員
主訴
目の乾きと疲れが常にあり、夕方になると充血して仕事に集中できない。特にエアコンの効いたオフィスで症状が強く出る。
生活背景
-
パソコン業務が1日8時間以上
-
昼食はパンやコーヒーで済ませることが多い
-
残業が続き、睡眠は5時間前後
-
体力が落ちやすく、休日は横になる時間が長い
東洋医学的分析
-
過労と睡眠不足で「気」が不足し、エネルギーが足りない
-
食生活の乱れと疲労で「陰(潤い)」も消耗し、乾きや充血につながる
→ 「気陰両虚型」のドライアイと考えられる
行ったこと
-
鍼灸:気を補い潤いを養う施術を週1回
-
生活改善:
-
昼食に温かい汁物とたんぱく質を追加
-
残業日は就寝前のスマホ使用を控え、睡眠時間を6時間以上確保
-
1時間ごとに休憩し、目を閉じて深呼吸を行う
-
経過
-
2週間で夕方の充血が軽減し、目の疲れが和らぐ
-
1か月で日常の乾きが軽くなり、集中力が持続するように
-
2か月後には、エアコン環境でも症状が以前ほど悪化せず安定
続きはnoteで
本編では、ドライアイのタイプ別の詳しい原因とケア方法、複数の実際の症例を紹介しています。
「目薬では追いつかない乾き」を根本から整えるヒントを探してみませんか?