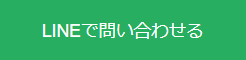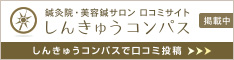夢が多くて眠りが浅い
20代女性・大学院生
主訴
眠っても夢が多く、朝の疲れが抜けない。レポートや研究発表の準備で緊張し、試験前は特に夢が増える。
生活背景
-
睡眠は6時間前後だが、夢をよく見て熟睡感がない
-
昼はパンや甘い菓子で済ませることが多い
-
長時間のデスクワークで運動不足
-
生理前に疲労感と集中力低下が目立つ
東洋医学的分析
-
勉強による思考の使いすぎと、食生活の乱れで「脾(消化の力)」が弱り、気血が不足
-
気血が足りないため「心(精神を落ち着ける働き)」を支えきれず、夢が多く眠りが浅くなる
→ 「心脾両虚型」の多夢と判断
行ったこと
-
鍼灸:脾を補って気血を養い、心を落ち着ける施術を週1回
-
生活改善:
-
夜は就寝前のスマホを控え、軽い散歩を習慣化
-
甘い菓子やカフェインを減らし、消化にやさしい食事を意識
-
経過
-
2週間で夢の回数が減り、朝の倦怠感がやや改善
-
1か月で試験期でも睡眠の質が保たれるようになり、集中力が向上
-
2か月後には熟睡できる日が増え、夢を覚えていないことも多くなった
続きはnoteで
本編では、「多夢」のタイプ別の詳しい原因と養生法、複数の症例の経過を解説しています。
「寝ても寝ても休まらない」方にとって、体質からの整え方を見つけるヒントになるはずです。
過剰な眠気
30代女性・事務職
主訴
仕事中に強い眠気が出て、午後は特に集中力が続かない。休日も昼寝をしないと夕方まで体が持たない。
生活背景
-
朝食を抜くことが多く、昼はパンやコーヒーで済ませる
-
冷たい飲み物をよく摂る
-
消化不良を起こしやすく、下痢や軟便が多い
東洋医学的分析
-
不規則な食事や冷飲食で「脾(消化機能)」が弱り、エネルギー源の気血が十分に作れない
-
そのため日中にエネルギー不足となり、強い眠気につながる
→ 「脾虚型」の嗜眠と判断
行ったこと
-
鍼灸:脾胃の働きを助け、気を補う施術を週1回
-
生活改善:
-
朝に温かい味噌汁やお粥を摂る習慣をつける
-
冷たい飲み物を常温・温かいものに変更
-
残業後は夜食を控える
-
昼休みに軽い散歩を取り入れ、消化を促進
-
経過
-
2週間で午後の強い眠気が軽減し、仕事がはかどるように
-
1か月で軟便が改善し、体が軽く感じられるようになる
-
2か月後には休日の昼寝が不要になり、生活のリズムが安定
続きはnoteで
本編では、嗜眠のタイプ別の詳しい特徴とケア方法、複数の実際の症例を解説しています。
「眠っても眠っても眠い」状態を見直すヒントを探してみませんか?
吃音
10代男性・高校生
主訴
授業で音読の際、最初の言葉が出にくい。緊張すると「か行」「た行」が特につかえる。友人との会話では比較的スムーズ。
生活背景
-
試験や発表の前に強い緊張を感じやすい
-
夜更かしで睡眠は5〜6時間
-
朝食を抜くことが多く、昼まで頭がぼんやりする
-
運動は部活動で週2回程度
東洋医学的分析
-
睡眠不足と食生活の乱れで気血の不足があり、声に力が出にくい
-
緊張が重なると気の流れが詰まり、言葉が出にくくなる
→ 「気滞」+「気血不足」の混合タイプ
行ったこと
-
鍼灸:胸の緊張をゆるめ、声を出しやすくする施術を週1回
-
生活改善:
-
就寝時間を1時間早め、睡眠を7時間確保
-
朝食に温かい汁物や軽いご飯を取り入れる
-
話す前に深呼吸を習慣づける
-
経過
-
2週間で授業中の音読が少し楽になり、発声がスムーズに
-
1か月で「か行」のつまりが減り、発表で最後まで話しきれた
-
2か月後、緊張は残るが言葉が出やすくなり、自信が戻ってきた
続きはnoteで
本編では、吃音のタイプ別の詳しい原因とケアの方法、複数の症例の経過を掲載しています。
言葉が出にくい背景を理解し、体と心の両方から整えるヒントを探してみませんか?
チック症
中学生の男の子
主訴
まばたきが頻繁で、時には小声で「うーん」とつぶやくような声のチックが出る。友人から指摘されて初めて気づいた。
生活背景
-
部活動のストレスが強く、帰宅後はスマホやゲーム漬け。
-
夜更かし(就寝は深夜12時以降)で、翌朝は寝坊ぎみ。
-
好きなスナックや冷たい炭酸飲料を好み、夕食は偏りがち。
東洋医学的分析
「体に熱(痰火)がこもりやすく、さらに消化力(脾)が弱まっている」タイプとして、「痰火内擾型」+「脾虚痰聚型」の混合型が疑われました。
対応と経過
-
食事は和食中心に改善し、スナック・冷たい飲み物を控えることを開始。
-
夜のスマホ使用を制限し、入浴後は読書や音楽などでリラックス時間を設定。
-
鍼灸では、痰や熱を取り除き心身を調える施術を週1回ほど継続。
→ 2週間ほどで、まばたきの頻度がかなり減少、声のチックも自然と少なくなる傾向が見られました。本人から「最近、気が楽」だという感想もあったそうです。
気になる方はこちらもぜひ!
この記事では、上記以外にもチック症の多彩なタイプや、家庭でのケアの工夫を詳しく解説しています。
詳しくは以下のnoteでどうぞ!
顔面神経麻痺
40代女性・営業職
主訴
左頬から口元にかけての麻痺。朝、洗顔中に水が口からこぼれ落ちて気づく。
生活背景
-
連日の残業と外回りで疲労が蓄積
-
冷たい飲み物やアイスを好み、夏でも冷房の風に直接当たる
-
睡眠は平均5時間、慢性的な肩こりと頭痛あり
東洋医学的分析
長時間の冷房と冷飲食で「風寒」が顔面部に侵入し、もともとの疲労と気血不足が重なって発症したタイプ。
対応と経過
-
気血の巡りと局所の筋肉機能を回復
-
生活面では冷飲食の制限と十分な睡眠を指導
-
2週間で口角の動きが改善し、2か月で会話時の違和感がほぼ消失
詳しく知りたい方はこちら
note本編では、顔面神経麻痺のタイプ別の見分け方や、実際の症例を解説しています。
発症直後の適切な対応が、回復のスピードを大きく左右します。